福岡県産婦人科医会主催
このプログラムは、「入門編」「基礎編」「応用編」とあり、私は今回「入門編」の研修を受けました。
自分のための記録として残します。
2024/2/18(日)九州大学医学部百年講堂
主スーパーバイザー:九州大学精神科子どものこころの診療部特任准教授 山下洋先生
副スーパーバイザー:九州大学精神科子どものこころの診療部医員 香月大輔先生
- 妊産婦の心理的変化を理解する
- 質問票を使ったメンタルヘルスのスクリーニングができる
▶ 育児支援チェックリスト
▶ エジンバラ産後うつ病質問表
▶ 赤ちゃんへの気持ち質問表
- 「アタッチメント形成に着目した妊産婦メンタルヘルスケア」吉田敬子先生
- 「地域保健福祉行政との連携・各領域でのスタッフ間との連携のノウハウ」相川祐里先生
アタッチメント(愛着):子どもが養育者のもとに身の安全を求めて近づいて、安全・安心を得ようとする行動
ボンディング:母親の子どもに対する情緒的な絆のこと
事例検討ワークショップ
各グループ6名ずつ。医師、助産師、看護師、保健師、心理師、それぞれ多職種が集まったグループで事例検討。
私のグループは、私以外皆さん助産師で、県外から参加された方もいらっしゃいました。
妊産婦さんの不安や自責などの気持ちに寄り添いながら、どんな情報を得ていけばよいか、どんな情報を提供できるか、それをおこなうタイミングはいつか、妊産婦のリスク要因だけでなく『強み』はなにかなど、助産師さんからの視点と知識はとても勉強になりました。
妊産婦さんのメンタルケアを産婦人科で抱え込まないためにも、行政や精神科との連携も大変重要です。妊産婦さんの気持ちに寄り添い受容共感と傾聴していきながら、「この人なら辛い気持ちを話せる」という信頼関係を作っていくことは、特に産後鬱による自殺防止のためにもとても大切です。

振り返ってみて
私は親子カウンセリングもしますが、この親子の心理的絆を一緒に育むことを意識しています。それには、クライアントさんが言いたいことを飲み込んで我慢してきたこと、母親を悲しませないように合わせてきたことなど、そのとき抑え込んだ感情に焦点をあて感情処理をします。
無意識に溜めてきた心のコップにある不快な感情に気づき、消化していくことで認知の変化が訪れます。カウンセリングでは、不快な感情を処理しながらクライアントさんのなかにある答えを一緒に探し、気づきとそれを表現することをお手伝いするという姿勢です。なぜなら『答えはクライアントさんの中にある』からです。
今回妊産婦さんのリスクだけでなくどのクライアントさんに対しても強みを見つけてアプローチするということはとても大切だと感じた研修会でした。

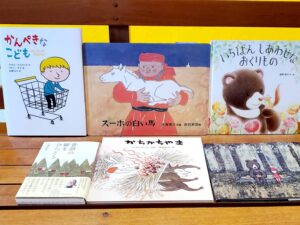

コメント